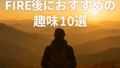雑誌『日経トレンディ』が選ぶ2024年のヒット商品ランキングで、投資信託として唯一トップ30入りしたのが「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、通称「オルカン」でした。このファンドは、初心者から経験豊富な投資家まで幅広い層に支持されています。その最大の理由は、「これ一本で世界中の株式に分散投資できる」という圧倒的な手軽さにあります。たとえば、米国・欧州・日本・新興国といったさまざまな市場に、難しい知識がなくても自動的にバランスよく投資できるのです。
また、オルカンは投資の基本である“分散”を自然と実現できる設計になっているため、ひとつの国や業種に偏らず、リスクを抑えながら長期的な資産形成が目指せます。私自身も「どこに投資していいか分からない」と悩んでいた時期にオルカンと出会い、「これなら自信を持って積立できる」と思えたのが始まりでした。
オルカンが連動するインデックスとは?
オルカンは MSCI ACWI(All Country World Index)という、世界47ヵ国・約2,500銘柄で構成される大型・中型株の株価指数をベンチマークにしています。この指数は先進国から新興国まで幅広い国と地域を対象にしており、世界経済全体の成長を反映する構造となっています。実際、MSCI ACWIは世界の株式市場の時価総額の約85%をカバーしており、1本のファンドでこれだけの分散が得られるのは非常に魅力的です。
たとえば、米国のハイテク企業、日本の製造業、欧州の消費財、新興国のインフラ企業など、地域もセクターも多様な企業に広く分散投資ができる点が、オルカンの最大の強みです。これにより、特定の国や企業に依存せず、長期的な成長を目指す投資スタイルを自然に実現できます。
私が感じた“安心感”
「全世界にまるごと投資している」という事実は、相場が荒れてもメンタルを保ちやすい――これが積立を数年続けて感じた最大のメリットです。特に、地政学リスクや経済危機など、特定の国や地域に影響する出来事が起きた際に「この地域がダメでも他がカバーしてくれる」という心の支えになります。過去には米国の利上げや中国の経済成長鈍化などで一時的な不安を感じたこともありましたが、世界全体に分散されているオルカンのおかげで、ポートフォリオ全体への影響は限定的でした。このような安心感は、長期投資を継続するうえで非常に大きな意味を持つと実感しています。
投資対象の地域・国をざっくり把握しよう
2025年3月末時点の地域別ウエイトは次のとおり
| 国・地域 | 比率 |
|---|---|
| 米国 | 64.55% |
| 日本 | 4.85% |
| 英国 | 3.39% |
| 中国 | 2.97% |
| カナダ | 2.88% |
| その他(40超の国・地域) | 21.61% |
(MSCI ACWI Factsheet、出典:MSCI公式サイト)
米国が6割超を占める一方で、日本・欧州・新興国もまとめてカバーしている点が特徴です。米国株の比率が高い分、円建てで保有すると為替が強く影響します。私自身、ドル高局面では基準価額が想定以上に伸びた一方、円高で評価額が伸び悩む場面も経験しました。
オルカンに組み込まれている主要銘柄
ACWIの上位銘柄は以下の通り(2025年5月末時点)
| 順位 | 企業名 | 比率 |
| 1 | NVIDIA | 4.10% |
| 2 | Microsoft | 4.03% |
| 3 | Apple | 3.74% |
| 4 | Amazon.com | 2.40% |
| 5 | Meta Platforms | 1.75% |
| 6 | Broadcom | 1.33% |
| 7 | Alphabet(Class A) | 1.24% |
| 8 | Tesla | 1.24% |
| 9 | Alphabet(Class C) | 1.07% |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC) | 0.98% |
ハイテク大手が上位を占めるものの、指数全体では金融・資本財・ヘルスケア・生活必需品・エネルギー・公益・通信サービス・不動産・素材・一般消費財・情報技術の11セクターにバランス良く分散されています。これにより、特定の業種に依存せず、各セクターの景気循環に対応できる安定的な運用が可能になります。たとえば、ハイテク株が不調でもヘルスケアや公益セクターが下支えするなど、相互補完的にリスクを分散できる点が、長期保有における大きな安心材料となっています。
値下げ実績は“半端じゃない”――信託報酬0.05775%の衝撃
| 年月 | 新旧信託報酬(税込・過去の推移) | 下げ幅 |
| 2018/7 | 0.15336% → 0.1530% | -0.00036pt |
| 2019/6 | 0.142% → 0.1144% | -0.0276pt |
| 2021/11 | 0.1144% → 0.10989% | -0.00451pt |
| 2023/9 | 0.10989% → 0.05775% | -0.05214pt |
eMAXIS Slimシリーズは「業界最安水準の運用コストを将来にわたって目指し続ける」と明言しており、実際に純資産が増加するたびに信託報酬の引き下げを積極的に実施してきました。これにより、投資家はファンドの成長とともにコスト面でのメリットを享受できる仕組みとなっています。
たとえば、オルカンの信託報酬はわずか0.05775%。これは、楽天・全米株式インデックスファンドの0.09372%や、SBI・Vシリーズの全世界株式ファンドの0.1133%と比べても、非常に低水準です。類似の全世界株式ファンドと比較しても、そのコスト競争力は圧倒的です。
私自身、毎月の積立を淡々と続けるなかで、信託報酬が大幅に引き下げられていたことに後から気づき、「何もしていないのにコストが下がる」ことに大きな驚きと感動を覚えました。この仕組みは、時間を味方につけてじっくり資産形成を目指す長期投資家にとって非常に心強く、運用効率の向上を自然と実現してくれるeMAXIS Slimシリーズならではの魅力だと感じています。
投資前に押さえておきたいリスク
| 主なリスク | 内容 | 実体験メモ |
| 価格変動リスク | 世界市場全体が下落すればオルカンも下がる | 2024年7〜8月の急落では円建てで▲12%を経験。それでも積立は継続した結果、半年でプラス域に回復しました。 |
| 為替リスク | 円高になると基準価額が目減りしやすい | ドル円が115→100円に戻った時、米国比率の高さから円建て評価額が2割近く揺れた |
| 地域集中リスク | 米国株が64%と高比率。米国市場の不調が直撃 | 米国の経済・政治イベント前には相場変動が大きくなることを実感 |
| 信託報酬 | 低コストでも長期では確実に効く | 0.05%台とはいえ、1,000万円運用なら年5,000円超のコスト。長期で侮れない |
ファンドの倒産リスクは?
投資信託は、投資家から預かった資産を信託銀行にて分別管理する仕組みになっているため、仮に運用会社が経営破綻しても、投資家の資産は信託銀行によって安全に保護されます。これは「信託分離保管」と呼ばれる制度に基づいており、法的にも守られています。そのため、ファンドそのものが「倒産して資産が消えてしまう」というリスクは極めて低く、基本的にはほぼ心配はないと考えられます。また、eMAXIS Slimシリーズのような大手運用会社(三菱UFJアセットマネジメント株式会社)が提供するファンドであれば、運用体制や管理体制も非常に整っており、透明性も高いため、より安心して長期保有が可能です。投資信託におけるリスクは主に市場変動や為替変動であり、運用会社の倒産リスクそのものは限定的です。
純資産総額の推移――6兆円突破の勢い
2025年6月13日時点の純資産総額は約6兆円。わずか3年前の2022年には3兆円程度だったことを考えると、驚異的なスピードで資金が集まっていることがわかります。これは、コストの安さや運用の透明性、そして何より「全世界に分散投資できる」という設計思想が、個人投資家の信頼を獲得している証とも言えるでしょう。
また、純資産の急増はスケールメリットを生み出し、さらなる信託報酬の引き下げにつながる好循環を生んでいます。まさに「成長しながら進化し続けるファンド」として、今後もますます注目を集めていくと予想されます。
私がオルカンを選び続ける“3つの決め手”
世界分散という精神安定剤
米中対立や◯◯ショックが起きても「全世界まるごと」で持っている安心感が大きい。どの地域が不調でも、他の地域が支えてくれる可能性があるという構造は、投資初心者にとって非常に心強いポイントです。また、オルカンは新興国市場も含んでいるため、将来的な成長性の取りこぼしも少なく、長期的には安定と成長の両立が見込めます。私自身、コロナショックやロシア・ウクライナ問題など突発的な事象が起きた際にも、この分散構造のおかげで大きく動揺せずに積立を続けられました。
信託報酬は常に最安クラス
受益者還元型の仕組みで、規模拡大=手数料ダウン。長期投資と相性◎。特に、オルカンは業界内でも数少ない「手数料を自動で引き下げてくれる」ファンドです。信託報酬は一見すると小さな差に見えますが、10年、20年と積み立てを続けた際の差は非常に大きくなります。この仕組みがあることで、投資初心者も安心して長期で付き合えるファンドと言えるでしょう。
どの証券会社でも買える“汎用性”
楽天証券・SBI証券・マネックス証券など、主要なネット証券でオルカンは取り扱われており、証券会社を問わず簡単に購入できるのが大きな魅力です。特に、新NISA制度がスタートしてからは、多くの証券会社でつみたて投資枠・成長投資枠の両方に対応しており、利便性が高まっています。また、将来的に証券会社を変更したくなった場合でも、オルカンは複数の証券会社で共通して取り扱われているため、新しい口座で同じファンドを使って積立を再開しやすいというメリットがあります。
※現行NISA制度では、NISA口座で一度購入した投資信託は、別の証券会社のNISA口座に“移す”ことが制度上できません。たとえば、楽天証券でNISA口座を使って購入したオルカンは、SBI証券など別の会社に引き継ぐことができないため、乗り換えを検討する際には十分に注意が必要です。
まとめ――“究極のど真ん中”を一本、長く握ろう。
-
世界約2,500銘柄へ一括投資できる分散ファンド
-
信託報酬0.05775%と“最安クラス”の運用コスト
-
純資産6兆円超、コストも信頼も年々向上中
最後に、オルカンは“放っておける”ファンド、つまり一度積立設定をしてしまえば日々の値動きに一喜一憂せず、長期保有に適しているファンドです。どれほど優れたファンドでも短期的な価格の上下や為替変動の影響を完全に避けることはできません。そのため、自分自身のライフプランや家計の状況、リスク許容度を冷静に見極め、無理のない範囲で投資を始めることが大切です。私は最初、月1万円から積立を始め、生活費や支出の見直しを通じて少しずつ投資額を増やしていきました。「余裕資金で、長期目線で続けること」は精神的な負担も少なく、結果としてFIREという目標に向けて着実に前進する力になったと実感しています。焦らず、着実に。コツコツ積み上げることが、豊かなFIREライフへの最短距離だと今では確信しています。
この記事は2025年6月時点の情報をもとに執筆しています。制度変更や手数料改定などの最新情報は必ず公式サイトや最新の交付目論見書でご確認ください。