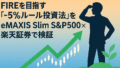FIRE(Financial Independence, Retire Early:経済的自立と早期リタイア)を目指すうえで、多くの方が気になるのが「税金」と「社会保険料」です。
株式投資で得た利益には通常20.315%の税金(所得税+住民税+復興特別所得税)がかかりますが、NISAを利用すれば非課税で運用が可能です。ただし、NISAには年間投資上限(生涯投資上限1,800万円)があるため、それだけでFIREを達成するのは難しく、多くの人が「NISA+特定口座」を併用して資産を築いています。
FIRE後は定期的な給与がなくなるため、生活資金をどのように確保し、どれだけ税金や社会保険料を抑えられるかが重要になります。税金の仕組みを理解しているかどうかで、毎月の出費は数万円単位で変わってしまうこともあります。つまり、FIREの成功は投資成績だけでなく、「税金と保険料の最適化」にかかっていると言っても過言ではありません。
そこで本記事では、FIRE後に所得税をゼロにし、住民税もゼロ、国民健康保険料を最低限に抑える方法を初心者にも分かりやすく解説します。具体的なシミュレーションや制度の背景も交えて紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
なお、2025年(令和7年分)の税制改正により基礎控除は合計所得金額に応じて段階化されていますが、本記事の計算は説明をシンプルにするため原則額の58万円を前提にしています。
所得税をゼロ(非課税)にする
まずは所得税から見ていきましょう。所得税は、働いて得た収入や投資利益に課される国税で、私たちの生活に直結する大きな支出のひとつです。制度の理解が浅いと「どれだけ収入を抑えればいいのか」「どんな控除を活用できるのか」が分かりにくく、結果として無駄に税金を支払ってしまうことになりかねません。FIRE後においては、わずかな税負担でも生活費に大きな影響を与えるため、正しい知識を持つことが重要です。
所得税には「給与所得控除」と「基礎控除」という2つの基本的な仕組みがあり、これらをうまく活用することで課税所得をゼロにすることができます。
給与所得控除:65万円
基礎控除:原則58万円(合計所得金額が低い場合は最大95万円)
つまり、給与が65万円以内なら自動的に非課税です。
計算式: 給与65万円 - 給与所得控除65万円 = 0円
さらに、給与が65万円を超えても基礎控除が使えるため、給与123万円(基礎控除が58万円の場合)までは所得税ゼロになります。
<計算式>
給与123万円 - 給与所得控除65万円 - 基礎控除58万円 = 0円
ただしポイントは、「給与を65万円以下に抑えると基礎控除を株の利益に使える」という点です。
給与65万円以下 → 株の利益に基礎控除58万円を使える
株の利益58万円まで非課税
つまり、給与65万円+株の利益58万円=合計123万円までなら、所得税はゼロで済みます。これはFIRE後にアルバイトやパートなどで少額の給与収入を得ながら、投資利益を組み合わせて生活する場合に大きな意味を持ちます。
住民税をゼロ(非課税)にする
次に住民税です。住民税は地方税として自治体に納めるもので、国に納める所得税とは別の仕組みになっています。仕組みはよく似ていますが、基礎控除額や計算方法に細かな違いがあり、特にFIRE後の生活ではこの差が重要になります。例えば、基礎控除額が所得税より少なく設定されているため、同じ水準の収入でも課税されるかどうかが変わるのです。
給与所得控除:65万円
基礎控除:43万円
そのため、給与65万円以下なら給与所得はゼロ。さらに、株の利益43万円までは非課税にできます。
<計算式>
給与65万円 - 給与所得控除65万円 = 0円
株の利益43万円 - 基礎控除43万円 = 0円
結論として、給与65万円以下+株の利益43万円以下なら、住民税はゼロとなります。
この仕組みを使うと、住民税が非課税になるだけでなく、「住民税非課税世帯」として認定されます。住民税非課税世帯になると、国民健康保険料の減免、国民年金の全額免除(申請制)、医療費の自己負担軽減、各種補助金や奨学金制度の優遇など、生活の安心感を高める制度を活用できるようになります。
住民税非課税世帯に関しては別の記事で紹介していますのでそちらを参照ください。
FIREを目指す人必見!住民税非課税世帯で節税&優遇制度の活用
国民健康保険料を最低保険料にする
最後に国民健康保険料についてです。国民健康保険料は、病気やケガなどの医療費をカバーする大切な制度であり、FIRE後の生活においても必ず支払わなければならない負担のひとつです。こちらは「ゼロ」にすることはできませんが、条件を整えれば最小限に抑えることが可能です。特に収入をしっかりコントロールすることで、自治体ごとに定められた最低保険料水準まで引き下げられるため、固定費削減の観点でも非常に重要なポイントとなります。
国保の所得計算でも、
給与所得控除:65万円
基礎控除:43万円
が適用されます。つまり、株の利益が43万円以内であれば国民健康保険料は「最低保険料」で済みます。
<計算式>
給与65万円 - 給与所得控除65万円 = 0円
株の利益43万円 - 基礎控除43万円 = 0円
実際の最低保険料額は自治体ごとに異なりますが、単身世帯であれば年間数万円、夫婦2人世帯であっても十数万円程度が目安です。FIRE生活における「固定費のひとつ」としてあらかじめ見積もっておくことが重要です。また、住民税非課税世帯の恩恵として、国民健康保険料の減免という優遇を受けられる点も見逃せません。
非課税条件のまとめ表
これを見れば一目で条件がわかります。以下に「給与収入」「株の利益」と控除を整理した非課税条件の早見表をまとめます。
| 区分 | 控除額 | 給与収入 | 株の利益(特定口座) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 給与所得控除65万円+基礎控除58万円 | 65万円以下 | 58万円以下 | 所得税ゼロ |
| 住民税 | 給与所得控除65万円+基礎控除43万円 | 65万円以下 | 43万円以下 | 住民税ゼロ |
| 国民健康保険料 | 給与所得控除65万円+基礎控除43万円 | 65万円以下 | 43万円以下 | 最低保険料 |
疑問?と注意点!
ここで「他にも所得控除があるのでは?」と疑問に思う方も多いでしょう。実際、基礎控除以外にも数多くの控除制度があり、うまく活用すれば税負担をさらに軽減することが可能です。例えば、社会保険料の支払い、家族構成、医療費の支出、保険契約の有無など、日常生活に密着したさまざまな条件によって適用できる控除が変わってきます。つまり、FIRE後に「どこまで課税を抑えられるか」は投資収益だけでなく、生活スタイルや支出の工夫によっても大きく左右されるのです。
-
社会保険料控除
-
配偶者控除/配偶者特別控除
-
扶養控除
-
生命保険料控除
-
地震保険料控除
-
医療費控除
-
小規模企業共済等掛金控除
-
寄附金控除(ふるさと納税など)
-
障害者控除
-
ひとり親控除
-
勤労学生控除
これらを利用すれば、株の利益をさらに増やしても所得税・住民税をゼロにできるケースがあります。例えば、基礎控除以外で合計100万円の控除を使えれば、株の利益=43万円+100万円=143万円まで非課税にできます。
ただし、注意すべきは国民健康保険料です。国民健康保険では基礎控除43万円しか認められず、他の所得控除は反映されません。つまり、税金はゼロにできても、国民健康保険料は上がってしまう可能性があるのです。
結論としては、所得税・住民税の軽減と国民健康保険料の負担増のバランスを見極めることが重要です。控除をフルに使って非課税枠を広げる戦略もあれば、あえて所得を抑えて国民健康保険料を最低限に留める戦略もあります。
▼国保料の試算はこちら
👉 国民健康保険料シミュレーションサイト
まとめ
本記事の内容を整理すると、次の通りです。
給与65万円以下に抑える
株の利益は43万円以下にする
NISA枠を活用して非課税運用する
この条件を守れば、
所得税=ゼロ
住民税=ゼロ
国民健康保険料=最低保険料
となり、FIRE後の生活費を大幅に抑えることが可能です。
例えば、特定口座での利益43万円+給与65万円=108万円に、さらに特定口座の元本43万円を加えると合計151万円となります。
※この元本43万円は、評価損益率100%(元本100万円に対して利益100万円)の投資信託を取り崩しているケースを想定しています。
これを12か月で割れば、月およそ12.6万円の生活資金を確保できる計算です。さらに、ここにNISAで積み上げた資産から毎月12万円を取り崩すと合計で月24.6万円の生活資金となります。
※この12万円という金額は、NISAの元本が1800万円あり、評価損益率100%で利益1800万円、合計3600万円となった場合に4%ルールに基づいて取り崩すと年間144万円=月12万円になる、という前提に基づいています。
加えて、住民税非課税世帯になれば、国民健康保険料の減免・国民年金の免除(申請制)・各種公的支援などの恩恵を受けられるのも大きなメリットです。教育費や医療費など、人生の中で大きな支出となり得る場面でも負担を軽減できるため、心理的な安心感にもつながります。
FIREは単に「働かない生活」ではなく、税金や社会保険制度を正しく理解して最適化することで、安心して「豊かな暮らし」を実現できます。
ぜひ、今日の記事を参考に、自分のFIREシミュレーションを進めてみてください。自分にとって理想的な収支バランスを見つけることが、長期的に安心できるFIRE生活への近道です。