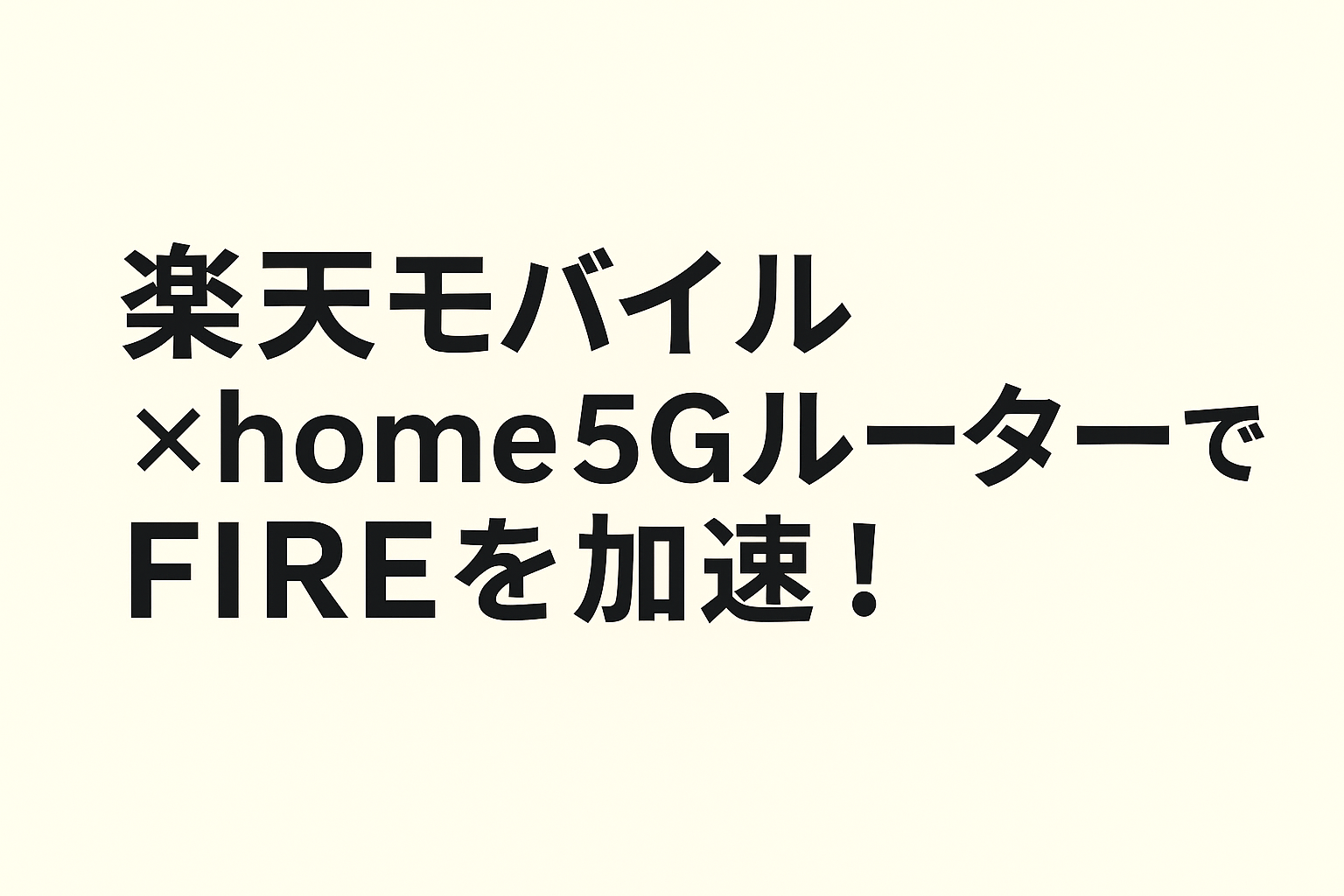FIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指している方にとって、生活費の中で大きな比重を占めるのが「社会保険料」です。家賃や食費など日々の生活費は節約や工夫である程度コントロールできますが、国民健康保険料などの社会保険料は法律で義務付けられているため、逃れることはできません。特に、会社員を辞めて無職になった後に加入する「国民健康保険料」は、想像以上に高額になることもあり、FIREを計画する際に見落としがちな落とし穴となりがちです。
この記事では、FIRE後に国民健康保険料がどのように決まるのか、その仕組みを理解しつつ、軽減措置を活用することでどれくらい負担が減らせるのかを具体的な事例とともに解説します。事前に知識を得ておけば、不安を減らし安心してFIRE生活をスタートできます。
FIRE後(無職)でも国民健康保険料はかかる?
まず大前提として、日本ではすべての人が「医療保険」に加入することが法律で義務付けられています。会社員や公務員であれば勤務先の健康保険に加入していますが、退職して無職になると自動的にその保険資格を失います。その際に加入するのが国民健康保険です。
つまり、FIREして収入がゼロになったとしても、国民健康保険には必ず加入しなければなりません。加入すれば保険料は必ず発生し、滞納すると延滞金が加算されたり、将来の医療費自己負担が増えたりといったリスクもあります。ですので「FIRE後は収入ゼロだから保険料もゼロになる」と誤解してはいけません。支払い義務があることを前提に、生活設計に組み込んでおく必要があります。
国民健康保険料は加入者数や前年所得で決まる
国民健康保険料は、世帯ごとの加入者数や前年の所得によって計算されます。ポイントは「前年の所得」に基づいて決まるという点です。そのため、今年FIREして収入がゼロになっても、前年に給与所得があればその所得に応じて計算されるため、FIRE初年度は高額な保険料になる可能性が高いのです。
保険料を決定する要素は以下のとおりです:
-
所得割 → 前年の課税所得に応じて算出
-
均等割 → 加入者1人あたり定額でかかる
-
平等割 → 世帯ごとに定額でかかる ※市区町村によってはなし
-
資産割 → 固定資産に応じてかかる ※市区町村によってはなし
これらの合計が年間の国民健康保険料になります。
国民健康保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割各市区町村によって税率や金額が異なるため、居住地をどこにするかによっても負担額は変わります。FIRE後に地方移住を検討している方は、こうした違いを調べるのも一つの戦略です。
所得割とは?
前年の課税所得に応じて算出されます。具体的な計算式は次のとおりです。
所得割 =(前年課税所得 - 43万円)× 所得割率前年の所得がゼロであれば、所得割もゼロになります。ただし、FIRE直後の1年目は前年に給与や事業所得があるため、その分の所得割が発生します。所得割がゼロになるのは、実際にはFIREして2年目以降です。計画を立てる際は「初年度は負担が重い」点に注意しましょう。
均等割とは?
均等割は加入者1人あたり定額でかかる保険料です。例えば夫婦2人で加入すれば2人分、子どもがいればその人数分も追加されます。つまり人数が多いほど負担が大きくなる仕組みです。
平等割とは?
世帯ごとに定額で課される保険料です。例えば「1世帯あたり3万円」といった形でかかります。ただし、設定していない自治体もあるため、居住地によって有無が異なります。
資産割とは?
固定資産税の課税額に応じてかかる部分で、主に不動産などを所有している場合に適用されます。これも市区町村によって導入しているところとそうでないところがあります。
令和7年度 国民健康保険税の参考例
地域によって国民健康保険料の算定方法や金額は異なります。ここでは例として、東京都港区、名古屋市、山形市を取り上げて比較してみます。
東京都港区の場合
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分※ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 7.71% | 2.69% | 2.25% | 12.65% |
| 均等割(1人あたり) | 47,300円 | 16,800円 | 16,600円 | 80,700円 |
※介護分は40~64歳の加入者のみ
※平等割、資産割なし
名古屋市の場合
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分※ | 合計 |
| 所得割率 | 8.77% | 2.60% | 2.27% | 13.64% |
| 均等割(1人あたり) | 49,728円 | 15,715円 | 15,906円 | 81,349円 |
※介護分は40~64歳の加入者のみ
※平等割、資産割なし
山形市の場合
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分※ | 合計 |
| 所得割率 | 9.42% | 2.79% | 2.08% | 14.29% |
| 均等割(1人あたり) | 22,800円 | 6,700円 | 13,600円 | 43,100円 |
| 平等割(1世帯あたり) | 26,700円 | 8,400円 | – | 35,100円 |
※介護分は40~64歳の加入者のみ
※資産割なし
このように地域によって所得割率や金額に差があることが分かります。例えば山形市の場合は均等割が安く抑えられている一方で、平等割が加わるため、世帯構成によっては都市部と同程度の負担となることもあります。
低所得世帯軽減措置について
FIRE後は収入がゼロになることが多いため、国民健康保険料が重くのしかかります。そこで活用できるのが「低所得世帯軽減措置」です。この制度では、世帯の総所得に応じて均等割や平等割が2割~7割減額されます。
軽減基準の目安
| 軽減割合 | 基準となる総所得金額の目安 |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者数※-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者数※-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者数※-1)以下 |
※給与所得者の数が1人以下の場合は1として計算
FIRE後にまったく収入がない場合、多くのケースで7割軽減が適用されます。例えば年間16万円程度の保険料が、軽減後には5万円以下にまで減額されることもあるのです。これは生活費全体の圧縮に大きく貢献し、安心してFIRE生活を送るための強力な味方となります。
令和7年度 国民健康保険料のシミュレーション
実際にどれくらいの金額になるのかをシミュレーションしてみましょう。条件は以下の通りです。
-
所得ゼロ
-
加入者2人(本人+配偶者)
-
加入者2人とも40~64歳
東京都港区の場合
-
所得割:0円
-
均等割:80,700円×2=161,400円
-
合計:161,400円 → 7割軽減後:48,200円※
名古屋市の場合
-
所得割:0円
-
均等割:81,349円×2=162,600円
-
合計:162,600円 → 7割軽減後:48,700円※
山形市の場合
-
所得割:0円
-
均等割:43,100円×2=86,200円
-
平等割:35,100円
-
合計:121,300円 → 7割軽減後:36,200円※
※7割軽減の詳細な計算は割愛
このように、収入ゼロでも均等割や平等割による負担が残りますが、軽減措置を活用すればかなり抑えられることがわかります。住んでいる地域によって負担感は違いますが、制度を理解し備えることで想定外の出費を避けられます。
自分の住んでいる地域の国民健康保険料を調べてみよう!
FIRE生活と健康保険料の位置づけ
国民健康保険料は、FIRE生活における「固定費」のひとつです。電気代や通信費と同様、毎年必ず発生する出費であり、避けることはできません。そのためFIRE計画を立てる際には、インデックス投資の利回りや生活費削減ばかりに注目するのではなく、こうした社会保険料を含めた総合的な収支計画を組むことが大切です。
また、医療保険は万が一の病気やケガに備える重要なセーフティネットでもあります。保険料を負担に感じるかもしれませんが、病院に安心して通える環境を維持するためのコストと考えれば、決して無駄ではありません。
まとめ
FIRE後は収入がゼロになるケースが多く、国民健康保険料の負担を不安に思う方も多いでしょう。しかし、軽減措置を活用することで、年間数万円程度まで負担を抑えることが可能です。
-
FIRE初年度は前年所得で保険料が高額になる
-
所得ゼロでも均等割や平等割は発生する
-
低所得世帯軽減措置により7割減額が可能
-
居住地や世帯人数によって負担額が変わるため、移住計画の参考にもなる
FIREを目指す方にとって、こうした制度を理解しておくことは安心材料になります。将来の生活費を見積もる際には必ず国民健康保険料を含めて計算し、資金を計画的に準備しておきましょう。制度を上手に活用し、不安を減らしてこそ、豊かなFIRE生活が現実のものとなります。
最後に、ここで紹介した金額や軽減措置の条件は自治体によって異なる場合があります。実際に加入する際は、必ずお住まいの市区町村役場や公式サイトで最新情報を確認しましょう。